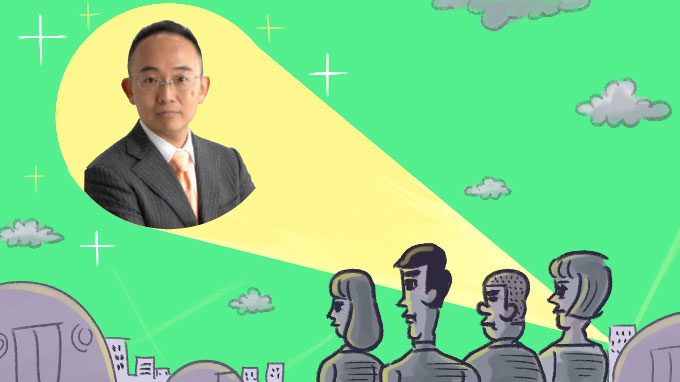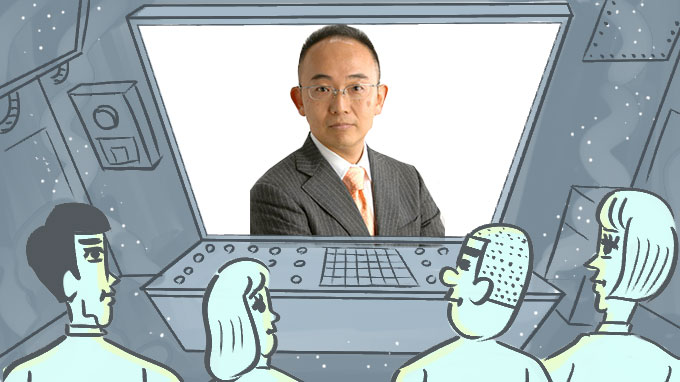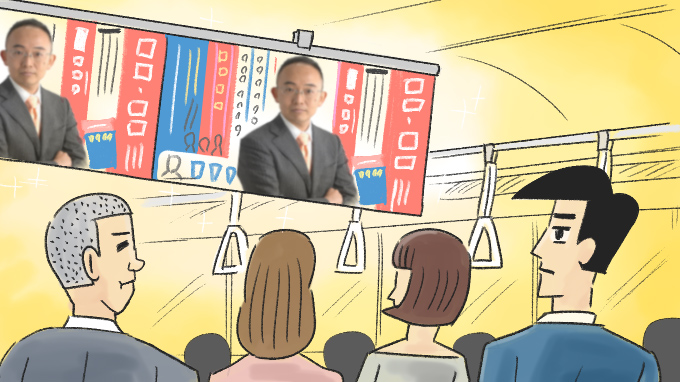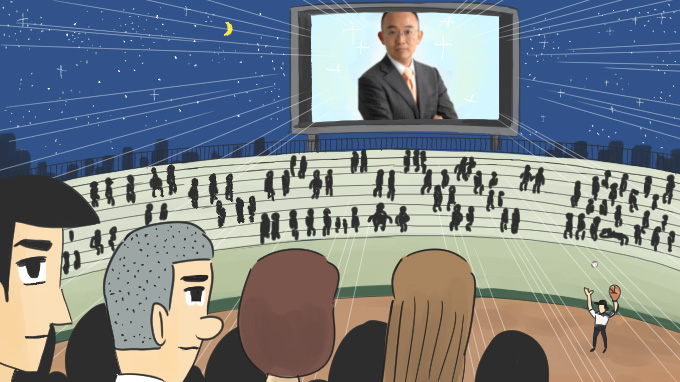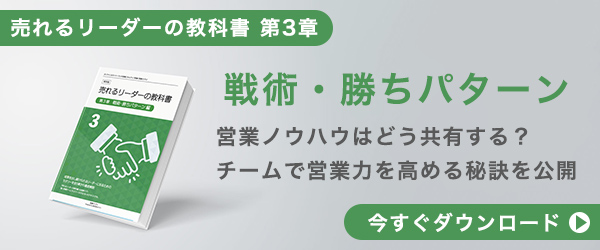事例勉強会のポイント
メタ認知で考える!営業の事例勉強会を有意義にするコツの紹介
営業リーダーの皆さんなら、商品やサービスの事例勉強会を企画し実施した経験を持つ方も多いと思う。ところがせっかく勉強会を実施してみても、事例の内容をお客様の状況に合わせて使いこなすことができるメンバーが少ないことに、落胆したことはないだろうか。
今回は、事例勉強会の留意点についてお伝えしよう。
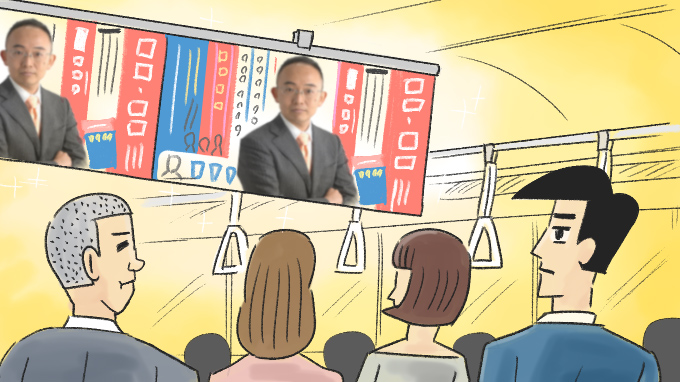
事例勉強会ではなく、「事例説明会」になっていないか?
私も仕事柄、お客様の事例勉強会なるものに陪席させてもらうことがあるのだが、ありがちなケースとしては、以下のような進め方が多い。
- 成功事例を担当した営業メンバーが、受注や導入に至るまでの経緯を説明
⇒営業面で苦労した点や工夫した点を中心に説明することが多い - お客様の声、評価ポイント、導入効果の説明
- 事例内容についての質疑応答
これでは事例勉強会ではなく、単なる「事例説明会」に過ぎない。確かに、案件内容を詳しく理解することはできるが、この進め方では、「この事例はこの営業場面で活用すると説得力がでる!」というレベルまで発想を広げて理解するまでには至らないことが多い。
これを専門的な言葉で言うと「メタ認知能力」という。1つの事象を、より高次元なレベルで客観的に捉えて、その意味を理解する力だ。
この「メタ認知」まで理解が深まらないと、「とても努力して受注して凄いなと思うけど、自分の営業にはあまり関係がないなあ…」という感想で終わってしまうのだ。
事例を4つ要素で整理し、活用イメージを膨らませよ!
事例には、次の4つ要素が含まれる。逆に、この4つの要素が含まれない場合は、事例勉強会のネタとしては適していない。
前回のコラムで紹介したリフォーム会社の「浴室乾燥機」の施工事例を引用すると、
- ニーズやお困りごとが生じた背景
⇒遊び盛りの小さな男の子がたくさんいる ベランダが狭い - 具体的なニーズやお困りごと
⇒洗濯物を干す場所がなく、室内だと乾きにくい
⇒洗濯乾燥機だと何度も乾燥しなければならず、手間と高熱費がかかる - お客様が感じた価値
⇒「浴室乾燥機」は、洗濯乾燥機よりも多くの衣類を早く乾かすことができた
⇒光熱費も下がった - 価値提供をもたらした商品サービスの機能特徴
⇒電気と比較してガスの方が熱効率が良い
⇒浴室の施工の工夫によって、多くの衣類がしわにならずに干せる
このように整理することができる。
事例勉強会は、ここから議論を発展させていくことがポイントだ。
- 子供がいなくても、頻繁に洗濯できない共働きとか、外に干せないとかで困っているご家庭にも当てはまるね!
- 洗濯乾燥機だと光熱費が気になるとか、ブレーカーが落ちてしまう、しわが気になると言っているお客様にも、説得力があるね!
というように、事例のニーズと提供価値を起点に、どのような営業場面で活用できそうか、そのイメージを膨らませていくことが重要なのだ。
特に、営業リーダーの皆さんは、上記の2、3、4が自社商品・サービスの営業先に展開しやすい事例を意識的にピックアップして、チームで行う勉強会の企画や議論をうまくリードしてもらいたい。
イラスト:室木おすし
この記事の情報は公開時点のものです。
営業の勝ちパターン・型づくりについてまとめた資料をダウンロード

営業サプリでは、この価値パターンのことを「営業の型」と定義しています。資料では「営業の型」の作り方から、作って終わりにしないための活用方法まで解説しています。
営業の型作り、お手伝いいたします
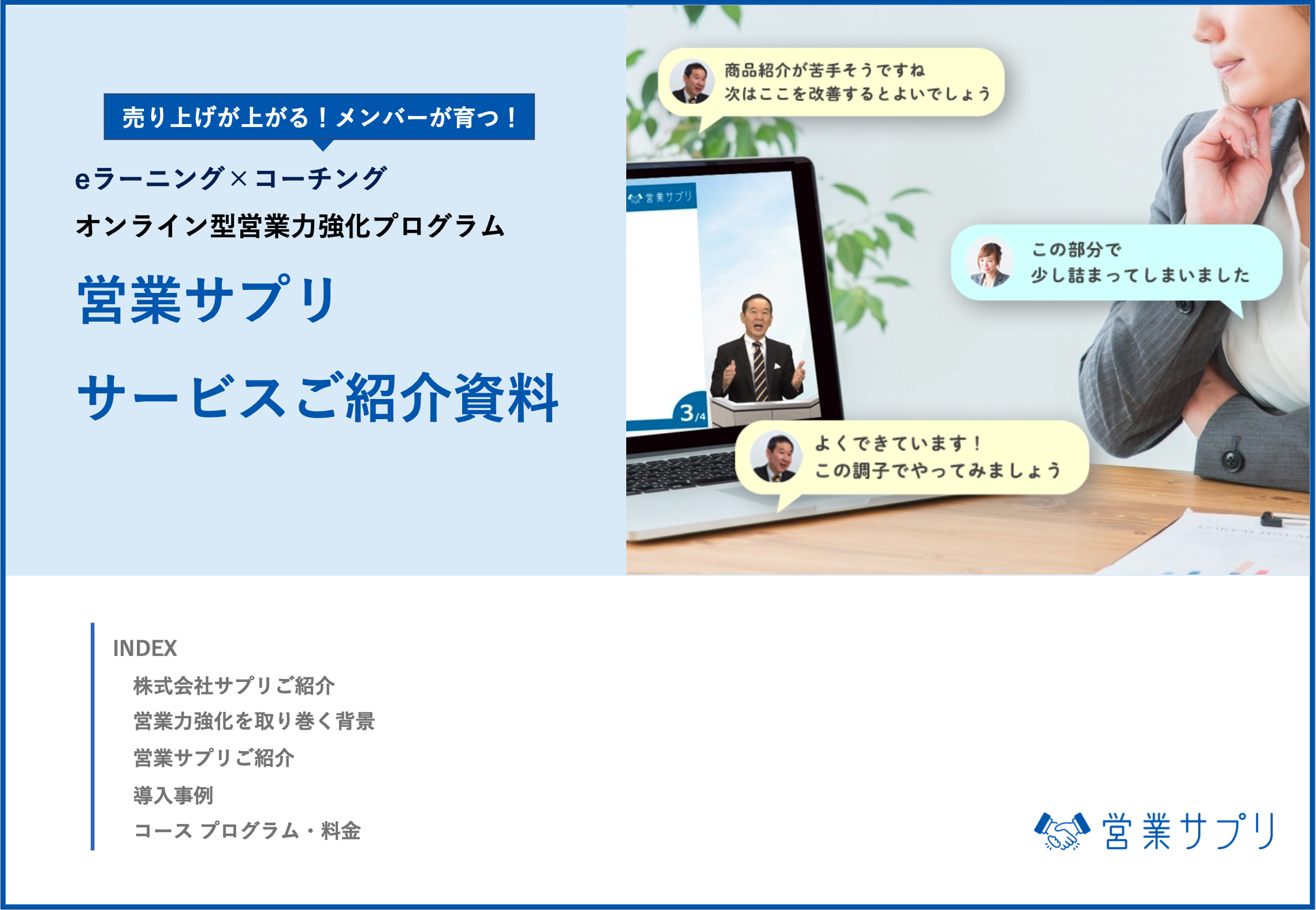
サプリでは、型化から教育までを一気通貫でご提供し、型を社内に浸透させるまでご支援いたします。また、各社様の課題に合わせて最適なカスタマイズをご提案させていただきます。
まずは資料をダウンロードしてご覧ご覧ください。