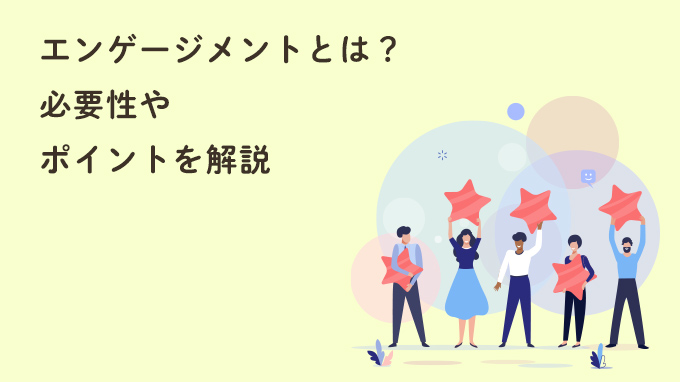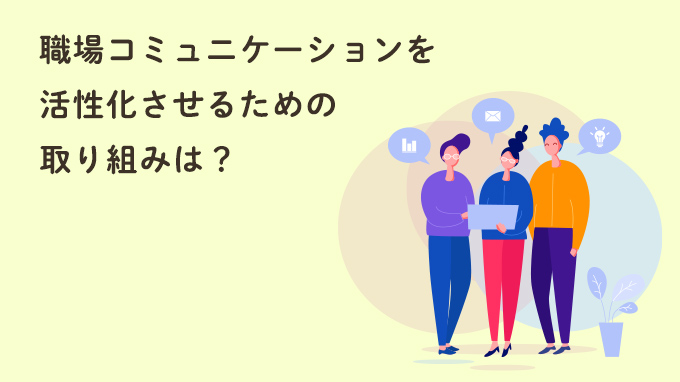心理的安全性とは?心理的安全性が高い組織がやっている4つのこと
心理的安全性とは、組織に所属する人物が自分の考えや気持ちを誰に対しても安心して発言や行動ができる状態のことです。
組織の生産性や定着率を高めたい方は是非ご一読ください。
→心理的安全性の高い組織を作るポイントを学べる「営業サプリ」部下育成スキルアップコースはこちら
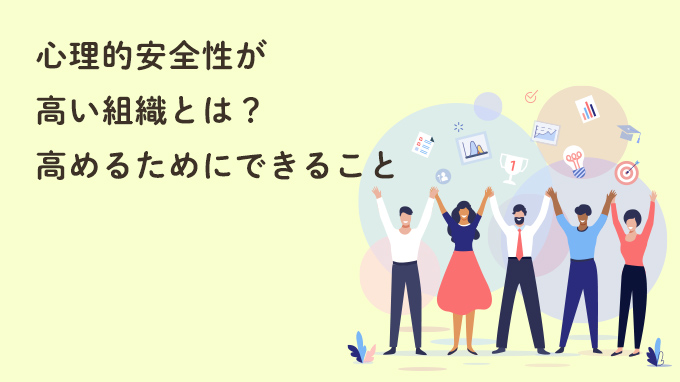
心理的安全性とは?
心理的安全性とは、組織に所属する人物が自分の考えや気持ちを誰に対しても安心して発言や行動ができる状態のことです。
語源は英語の「psychological safety(サイコロジカル セーフティ)」であり、これを和訳して日本では「心理的安全性」と呼ばれるようになりました。1999年に米ハーバード大の教授であったエイミー・エドモンドソンによって提唱された概念です。
このチーム(組織)内では、メンバーの発言や指摘によって人間関係の悪化を招くことがないという安心感をメンバーが持っていることが重要なポイントです。
心理的安全性が高い状況であれば、質問やアイディアを提案しても受け止めてもらえると信じることができ、率直に発言することができます。
逆に心理的安全性が低い状況であれば、自分の発言に自信が持てず、例え意見を促しても出てこない状態になります。
言い換えると、会議での意見交換や発言の活発さが心理的安全性のバロメータとして捉えることができます。
Googleが「生産性が高いチームは心理的安全性が高い」との研究結果を発表したことから注目されており、心理的安全性を高めることで個人や組織の効果的な学習や革新につながると期待されています。
心理的安全性が注目されている背景
Google社が2012年から2015年の4年間に生産性が高いチームの特徴を明らかにするためのプロジェクトを行いました。
社内の数百に及ぶチームや組織を対象にしたこの「プロジェクトアリストテレス」の研究結果を2016年に発表。
「心理的安全性の高いチームのメンバーは、離職率が低く、他のチームメンバーが発案した多様なアイディアをうまく利用でき、収益性が高く、マネジャーから評価される機会が2倍多い」ということが判明したのです。
生産性の高いチームは心理的安全性の高いチームであると明らかにされたことで、世界中で一気に認知度を高めました。
心理的安全性が低い職場で生まれるデメリットと4つの要因
反対に、心理的安全性が低い職場ではどのような問題が起こるのでしょうか。
それは、職場やチームで発言がしにくくなり、課題やミスがあっても誰にも相談が行えず自分で抱え込み、結果的に離職やチームの生産性が大きく減少することとなります。
心理的安全性が低くなる原因として、4つの不安があります。
エドモンドソンがスピーチフォーラム「TED」で紹介した「4つの心理的安全性を損なう要因と特徴行動」について紹介します。
(1)無知だと思われる不安(Ignorant)
質問や確認をしたくても「こんなことも知らないのかと思われないか」と不安になり、その結果、気になることがあっても質問しづらくなります。
(2)無能だと思われる不安(Incompetent)
ミスや失敗した時に「仕事ができないと思われるのでは」と不安になり、自分の失敗や弱点を認めず、ミスを報告しないようになります。
(3)邪魔をしていると思われる不安(Intrusive)
自分が発言することで「話の邪魔をしていると思われないか」不安になり、提案や発言をしなくなります。
(4)ネガティブだと思われる不安(Negative)
改善を提案したくても「他の人の意見を批判していると否定的に捉えられるのでは」と不安になり、現状の批判をせず、意見があっても言わなくなります。
心理的安全性が高い職場で生まれるメリット
心理的安全性が高い組織はメンバー間のコミュケーションも活発になり、仕事の質の上昇にも繋がります。
仕事をする上で、チームメンバーとの関係性が良好かどうかは、ポテンシャルを最大限発揮し、より良いパフォーマンスができるかに大きく影響します。また、チームとの信頼関係があれば、仕事における目的達成に向けて寄り道せず進行させることができるでしょう。
ここでは、心理的安全性を高めることによる効果をより詳しく見ていきましょう。
コミュニケーションが活発になり、情報やアイデアの共有が促進される
チーム間で信頼し合えている環境では、コミュニケーションが活発になり、仕事の生産性の向上に繋がります。
これは、無責任に自分の発言を増やすわけではなく、自分に非があった場合は非を認めやすくなり、質問を気軽にすることができたり、積極的にアイデア・意見を出すことができたりするということです。気軽でありつつも重要なコミュニケーションが頻繁に起こることで、結果的に情報やアイデアの共有が促進されます。
メンバーのパフォーマンスが向上し、成果を最大化できる
チーム内で不和があれば、対人関係について気を使い、労力を払うために、仕事の達成にむけて能力の100%を出すことができなくなります。対人関係について不安なく、気持ちよく仕事ができれば、最大限ポテンシャルを発揮することができるため、成果を最大化できます。 また、そのような良好なチーム環境での仕事の場合、モチベーションの維持についても好影響があるといえるでしょう。
責任感や関心が芽生え、人材の定着率が高まる
意見をする不安がないということは、やってはいけないことについても指摘できる環境であるということです。そのため、自身の仕事に対して、過大でも過小でもない、分相応かつ等身大の責任感が生まれます。意見できないがために上司や同僚のせいにしたり、または押し付けられることによって過大な責任感が生まれたりといったことを回避できます。
また、ポジティブな環境下でチームメンバーと意見を交換し合えることで、新たな知識を得るチャンスも増え、さまざまな関心が芽生える可能性もあります。 円滑なコミュニケーションの結果、メンバー同士の関係が深まることも指摘できます。チームである意識はモチベーションにも繋がり、やりがいを感じることができる場面が増えるでしょう。結果的に、人材が定着しやすい環境になります。
心理的安全性の高い組織を作るためにできること
実際に心理的安全性の高い組織をつくるには、組織・チームを率いるリーダーが率先してムードを高める必要があります。チーム内の近いところに信頼でき、見本となる姿を示すことで、チームにとってプラスの影響が出ます。そのために気をつけるべきポイントについてご紹介します。
リーダーがビジョンを持つ
心理的安全性の高い組織をつくるためには、まずリーダーの意識が必要です。自覚的な率先した環境作りによって心理的安全性は高めることができ、ひいては生産性の向上に繋がります。チームメンバーに共有しやすく、メンバーも同調することができるため、自身できちんと言語化し理解しておきましょう。
一方で、ビジョンのズレや、気遣いの方向性のズレなどが起こってしまうと、強い発言をしづらい優しい雰囲気はあるぬるま湯的なチームや、空気を読みすぎて反論意見がそもそも出てこないチームになる恐れもあります。ズレが起こった際に早めに対処できるよう、事前に明確なビジョンを持つようにしましょう。
お互いの存在を承認・尊重する
心理的安全性の確保の大前提として、チームメンバーはお互いにリスペクトし合える関係である必要があります。
何かネガティブな反応が返ってきそうな発言や行動をチームメンバーがした際に、実際に相手を貶したり、非難したり、見下すような態度をとるメンバーがいれば、信頼関係は一気に崩れてしまいます。
お互いの存在について、自身とは異なる他者であることを理解し、異なる意見であっても一度受け入れることが心理的安全性の確保には必要不可欠です。
1on1で腹を割って話をする機会を設ける
深い信頼関係を構築するには、日頃からコミュニケーションを多く取る必要があります。小さな変化や客観的なフィードバックを重ねることで、少しずつ信頼関係を築いていくことが肝要です。
また、チームとして複数人でいる場合のみのコミュニケーションでは、深い信頼関係を築くことは難しいでしょう。1on1での対話は、お互いの理解度を深め、その後の仕事を進める上でいい影響があるので、チームが始動してからできるだけ早いうちに機会を設けるようにしましょう。
自分を大きく見せようとしない
等身大のメンバーの姿で関係を築かせようとする中、自身のみが猫を被っていたり、見栄を張っていてはフェアではありません。また、素直に自分の非を認めたり、相手を尊敬・尊重したりすることが心理的安全性に繋がるため、自身を大きく見せるよう振る舞うよりも自然体で相手とコミュニケーションを重ねる方が、目指す職場環境への近道となります。
また、本来の自身と異なるキャラクターを見せる、忙しそうに振る舞うなど、自分を大きく見せようとする行動は、相談のしやすい職場づくりと反対の方向性であることを理解する必要があります。
営業サプリで心理的安全性の高い組織を作るポイントを学びませんか?
ここまでご説明してきたように、部下とのコミュニケーションの改善は心理的安全性を高める上で欠かせません。営業サプリ「部下育成スキルアップコース」では、考えさせるスキル、問いかけるスキル、フィードバックスキルといった、部下とのコミュニケーションを円滑にして心理的安全性を高め、育成効果をも高めるスキルを学ぶプログラムが用意されています。
・部下を信じ切れず、細かくマネジメントをしていたら煙たがられてしまった
・逆に、放置しすぎてうまくコントロールできなくなってしまった
といった経験をお持ちの方にはぜひご受講いただきたいです。詳しくは資料をご覧ください。
メンバー育成に関する資料をダウンロード

メンバー育成に関するノウハウをeBookにまとめて無料配布しています。簡単なフォームに入力するだけでダウンロードしていただけます。ぜひご覧ください。
\3分でわかる/
営業サプリ「部下育成スキルアップコース」紹介資料 ダウンロード
こちらのフォームにご入力ください(入力時間1分)。*は必須項目です。
- 1. 事業者の氏名又は名称
- 株式会社サプリ
- 2. 個人情報保護管理者の氏名又は職名、所属及び連絡先
-
個人情報保護管理者 代表取締役 酒井雅弘
info[at]sapuri.co.jp
[at]を@マークに変換してお問い合わせください。 - 3. 取得した個人情報の利用目的
- 当該フォームで取得した個人情報は、お問い合わせに関する回答、ご請求いただいた資料の送付、メールマガジンの配信等の目的で利用いたします。また、当社のサービスに関するご案内にも利用させていただくことがございます。
- 4. 当社が取得した個人情報の第三者への委託、提供について
- 当社は、ご本人に関する情報をご本人の同意なしに第三者に委託または提供することはありません。
- 5. 個人情報保護のための安全管理
-
当社は、ご本人の個人情報を保護するための規程類を定め、従業者全員に周知・徹底と啓発・教育を図るとともに、その遵守状況の監査を定期的に実施いたします。
また、ご本人の個人情報を保護するために必要な安全管理措置の維持・向上に努めてまいります。 - 6. 個人情報の開示・訂正・利用停止等の手続
-
ご本人が、当社が保有するご自身の個人情報の、利用目的の通知、開示(第三者提供記録の開示も含みます)、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を求める場合には、下記に連絡を頂くことで、対応致します。
<個人情報お問合せ窓口>
株式会社サプリ 個人情報お問合せ窓口
info[at]sapuri.co.jp
[at]を@マークに変換してお問い合わせください。 - 7. ご提供いただく情報の任意性
- 個人情報のご提供は任意ですが、同意を頂けない場合には、第3項にあります利用目的が達成できない事をご了承いただくこととなります。
- 8. 当社Webサイトの運営について
-
当社サイトでは、ご本人が当社Webサイトを再度訪問されたときなどに、より便利に閲覧して頂けるようCookieという技術を使用することがあります。これは、ご本人のコンピュータが当社Webサイトのどのページに訪れたかを記録しますが、ご本人が当社Webサイトにおいてご自身の個人情報を入力されない限りご本人ご自身を特定、識別することはできません。
Cookieの使用を希望されない場合は、ご本人のブラウザの設定を変更することにより、Cookieの使用を拒否することができます。その場合、一部または全部のサービスがご利用できなくなることがあります。
この記事の情報は公開時点のものです。