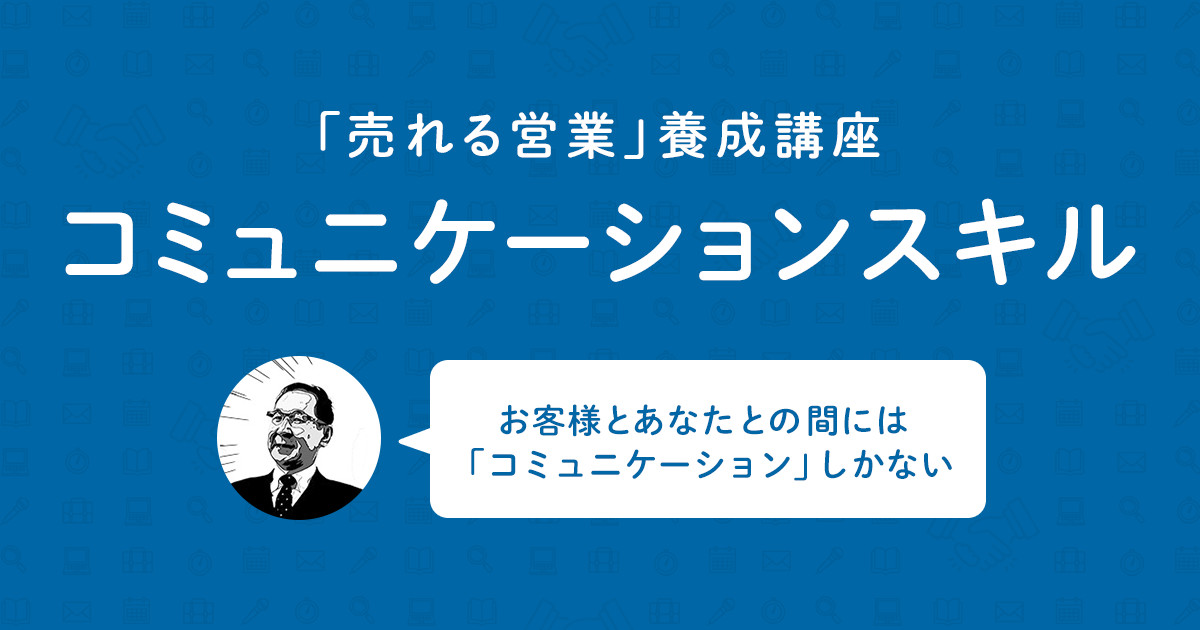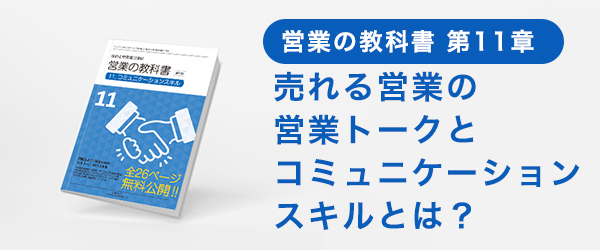顧客の課題を裏から把握する方法
売れる営業の情報収集法知ってますか?ヒアリングと「裏取り」で顧客の課題抽出
ジャーナリストや捜査関係者の間でよく「裏を取る」という言葉が使われる。情報や供述の真偽を確認するという意味だが、実は“売れる営業”が行っている情報収集や顧客の課題の抽出とは、ヒアリングというよりこの「裏を取る」行為に近い。
今回はその方法について紹介する。

商談相手から直接「裏を取る」方法
まずは直接、商談相手とのコミュニケーションの中で「裏を取る」際のコツから。
基本的に最も重要なのが、相手が「言っていること」を鵜呑みにするのではなく、「その背景」を明確に把握するまで聞き切ること。
具体例としては相手の「言っていること」が;
- 事実なのか
- 個人的意見なのか
- 推測なのか
をより分ける質問をして、必ず「裏を取る」こと。業績が低迷している営業パーソン、ヒアリングが下手な営業パーソンは個人的意見や推測に振り回されていることが多いので、ここは最初に注意したいポイントだ。
同様に課題を引き出せたとしても、それが;
- 現場の課題なのか
- マネージャークラスの課題なのか
- 役員クラスの経営課題なのか
の差に注意しながら情報を収集していきたい。もちろん、それらすべてに共通する課題であれば案件化するが、現場の課題をマネージャークラスや役員クラスは「課題」ではなく「愚痴」「その位のことは現場で片付けられること」と判断して案件化しないケースも少なくないので、「誰が」そのことを課題と言っているのかを判別して対応しなければならない。
それらの確かめ方、「裏の取り方」を紹介しておくと、推測して確かめる、いわゆる「鎌をかける」方法が代表的だ。
「確認質問」とも言われるが、「一点、確認なのですが、今、課長がおっしゃったクラウド化のお話はすでに中期経営計画(中計)的な計画に織り込み済みになるのでしょうか?」といったような言い方だ。
計画化されていれば、既に全社課題として案件化する可能性が高いし、「いや、まだそこまでは…」ということであれば、部門内での検討段階か課長の問題意識のレベルなので、その上位層の見解が情報として必要になってくる。
その際には自社の役員やトップを使って、顧客の役員、部長レベルの情報を取ってもらう方法や自社のソリューションや技術情報を用いて、相手に役立つ情報提供や提案を通じて、案件の優先順位を高める動きを進めて行きたい。

間接的に「裏」や情報を取る方法
次に商談相手からではなく間接的に「裏付け」や情報を収集する方法を3つ紹介しておきたい。
1)相手の別の部署の人に尋ねる
例えば、営業の窓口が設計部で6課体制の場合、1課の課長に3課の状況を聞いたり、3課の課長に資材部のことを聞いたりする方法だ。
不思議なもので、自分の部や課のことについては余り話さないのに、噂話同様に他部門のこととなると、いきなり雄弁になる人もいるし、逆に自部門については情報交換がてらに、ある程度話してくれるものの、他部門については一切口にしないのがマナーとしている人もいるので、ここは相手の特性を考慮しつつ進めたい。
2)ステークホルダーに尋ねる
具体的には相手の取引先や紹介者、仲介者に尋ねる方法。特に相手の顧客からはタイムリーでリアルな情報が入るので、ことあるごとに情報網を築いていきたい。
3)同業者との情報交換
業界や企業によっては同業者との情報交換が禁止されている場合もあるが、逆に定期的に情報交換の機会を設けている業界もあるので、ここは業界ルールに従って欲しい。
あるいは業界団体で法人組織を設けているケースでは、そこの役員などを通じて最新情報を入手しておきたい。
コミュニケーションスキルをまとめた資料をダウンロード

この記事の内容を含めた、コミュニケーションスキルをeBookにまとめて無料配布しています。簡単なフォームに入力するだけでダウンロードしていただけます。ぜひご覧ください。
私が開発した「営業サプリ」で営業メンバーを育てませんか?

ここで述べているノウハウやスキルは、読んだだけでも充分勉強になります。しかし、これだけでできるようになるわけではありません。実際の営業場面で「できる」ようになるためには『実践とフィードバック』が必要になります。
私が株式会社サプリと開発した『営業サプリ 売れる営業養成講座』は、営業パーソン自身の営業を前提に実践しながらオンラインで学ぶコースです。しかも専門コーチがマンツーマンで指導する仕組みになっています。
売れる営業パーソンになるスキル大全を身につけるオンライン研修、『営業サプリ』で「売れる」営業パーソンを育てませんか。さあ、営業サプリで営業組織を強くしましょう!
\3分でわかる/
営業サプリ紹介資料 ダウンロード
こちらのフォームにご入力ください(入力時間1分)。*は必須項目です。
- 1. 事業者の氏名又は名称
- 株式会社サプリ
- 2. 個人情報保護管理者の氏名又は職名、所属及び連絡先
-
個人情報保護管理者 代表取締役 酒井雅弘
info[at]sapuri.co.jp
[at]を@マークに変換してお問い合わせください。 - 3. 取得した個人情報の利用目的
- 当該フォームで取得した個人情報は、お問い合わせに関する回答、ご請求いただいた資料の送付、メールマガジンの配信等の目的で利用いたします。また、当社のサービスに関するご案内にも利用させていただくことがございます。
- 4. 当社が取得した個人情報の第三者への委託、提供について
- 当社は、ご本人に関する情報をご本人の同意なしに第三者に委託または提供することはありません。
- 5. 個人情報保護のための安全管理
-
当社は、ご本人の個人情報を保護するための規程類を定め、従業者全員に周知・徹底と啓発・教育を図るとともに、その遵守状況の監査を定期的に実施いたします。
また、ご本人の個人情報を保護するために必要な安全管理措置の維持・向上に努めてまいります。 - 6. 個人情報の開示・訂正・利用停止等の手続
-
ご本人が、当社が保有するご自身の個人情報の、利用目的の通知、開示(第三者提供記録の開示も含みます)、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を求める場合には、下記に連絡を頂くことで、対応致します。
<個人情報お問合せ窓口>
株式会社サプリ 個人情報お問合せ窓口
info[at]sapuri.co.jp
[at]を@マークに変換してお問い合わせください。 - 7. ご提供いただく情報の任意性
- 個人情報のご提供は任意ですが、同意を頂けない場合には、第3項にあります利用目的が達成できない事をご了承いただくこととなります。
- 8. 当社Webサイトの運営について
-
当社サイトでは、ご本人が当社Webサイトを再度訪問されたときなどに、より便利に閲覧して頂けるようCookieという技術を使用することがあります。これは、ご本人のコンピュータが当社Webサイトのどのページに訪れたかを記録しますが、ご本人が当社Webサイトにおいてご自身の個人情報を入力されない限りご本人ご自身を特定、識別することはできません。
Cookieの使用を希望されない場合は、ご本人のブラウザの設定を変更することにより、Cookieの使用を拒否することができます。その場合、一部または全部のサービスがご利用できなくなることがあります。
この記事の情報は公開時点のものです。