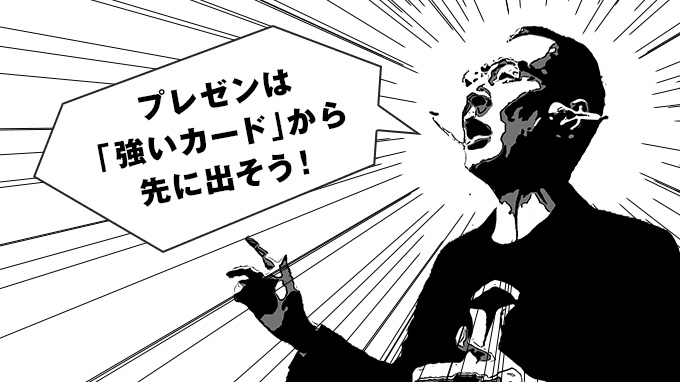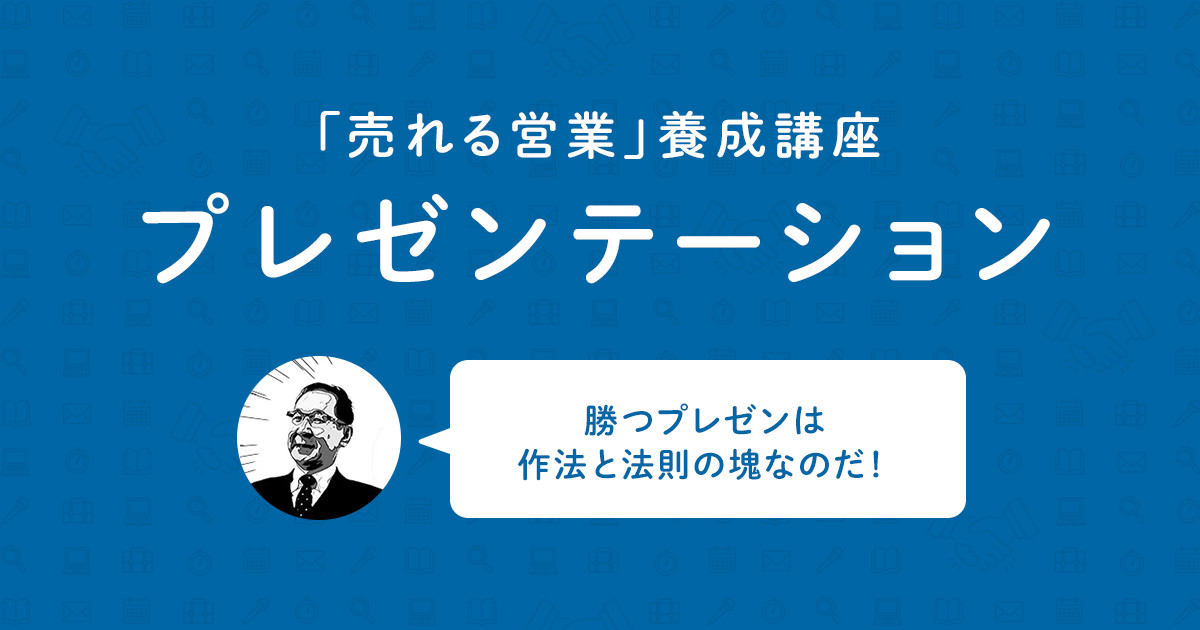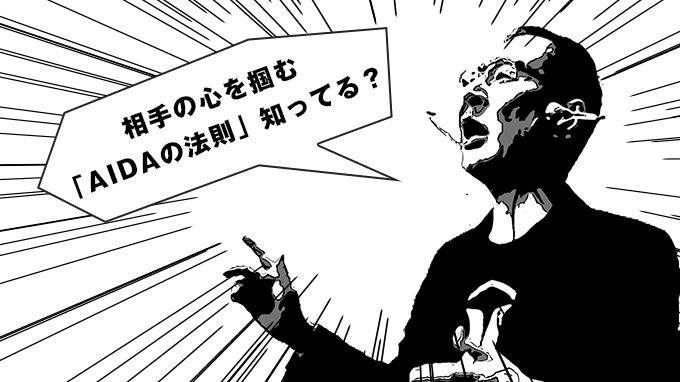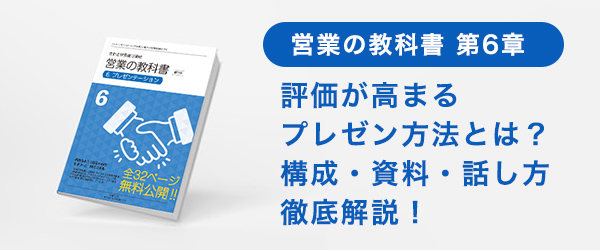プレゼンテーション 概論
【プレゼンテーション徹底解説】構成・話し方・資料作成の基本から営業で成果を出す方法まで
プレゼンテーションは単なる情報共有の場ではなく、相手に行動を促し、信頼を築く重要な手段です。本記事では、聞き手に響くプレゼンを行うための基本から応用まで、構成・資料・話し方の3つの観点で具体的なポイントを解説します。
プレゼンテーションとは?
プレゼンテーションとは、情報を整理して伝え、相手の理解・共感を得ることで行動を促すビジネスコミュニケーション手法です。スライドや資料を活用しながら、聞き手の状況に応じて内容を最適化することが求められます。会議や提案、営業の場など、あらゆるビジネスシーンで活用されています。
プレゼンテーションの目的
プレゼンテーションの最終的な目的は、聞き手に「行動してもらうこと」です。たとえば、商品を購入してもらう、提案を採用してもらう、理解や共感を得るといった具体的な成果に結びつけることが重要です。そのためには、スライドや資料で伝える情報を整理し、相手の立場に立ったメッセージ設計が不可欠です。単なる説明や発表ではなく、「相手がどう受け取り、どう動くか」を意識した構成が求められます。
プレゼンテーションの語源
「プレゼンテーション」は英語の「present=プレゼント」に由来し、「贈り物」や「提示すること」を意味します。現代のビジネスにおいては、情報やアイデアをわかりやすく、魅力的に提示する行為を指し、話し方と資料を組み合わせて聞き手に価値を届ける手段として定着しています。
プレゼンテーションと発表の違い
「発表」は情報を一方的に伝えるのに対し、「プレゼンテーション」は相手との対話を意識した双方向のコミュニケーションです。
プレゼンでは、聞き手の関心や課題に寄り添った内容構成が不可欠で、スライドや資料もそれに合わせて設計されます。ビジネスにおいては、共感や信頼を得ながら、最終的に相手の行動を引き出すことが成功のカギとなります。
成果につながるプレゼンテーションとは?
顧客から高く評価される「成果につながる」プレゼンテーションには、いくつかの共通点があります。ここでは、特に重要な3つのパターンをご紹介します。
明確な目的を持ったメッセージ
プレゼンテーションは、単に情報を伝えるだけではなく、ビジネスの目的に沿ってメッセージを発信することが重要です。聞き手に「何を理解してほしいのか」「どのような行動を取ってほしいのか」といった目的を明確に設定することで、伝える内容に一貫性が生まれ、資料やスライドの構成も効果的になります。目的が曖昧なプレゼンは、情報が散漫になり、相手に意図が伝わりにくくなるため注意が必要です。
聞き手のニーズを意識した内容設計
良いプレゼンテーションは、常に聞き手の立場に立ち、そのニーズや関心に寄り添った内容で構成されています。相手が求めている情報や解決策を事前にリサーチし、それに応じたスライドや資料を準備することがポイントです。例えば、業界特有の課題や具体的な成功事例を取り入れることで、聞き手の共感を得やすくなります。聞き手中心のアプローチが、ビジネスで成果を出すプレゼンの基本です。
論理と感情のバランス
データやファクトに基づいた論理的な説明は、プレゼンテーションの信頼性を支える要素です。しかし、それだけでは聞き手の心に残りません。感情に響くエピソードや視覚的に訴えるスライドを組み合わせることで、より印象的なプレゼンを実現できます。たとえば、実際の成功事例をストーリーとして語ることで、相手に共感を与え、行動につなげる力が高まります。論理と感情のバランスが、聞き手を動かすプレゼンのカギとなります。
営業プレゼンテーションならではのポイント
営業におけるプレゼンテーションでは、単なる情報の説明にとどまらず、「顧客の課題解決」や「ビジネスパートナーとして選ばれること」を目的に、以下の3つのポイントを意識することが重要です。
課題解決や問題解決のための「名案」や「兆し」、「ヒント」がある
営業のプレゼンテーションは、商材やサービスの特徴を説明するだけでなく、聞き手である顧客が直面している課題や問題をどう解決できるかを明確に示す必要があります。プレゼンの目的は、相手の立場に立った提案を行い、「この情報が自社の課題解決に役立つ」と思ってもらうこと。スライドや資料を活用し、自社商材がどのように価値を提供できるのかを、具体的なヒントや兆しとして伝えましょう。
任せてみたくなる「+α」もしくは「何か」がある
競合が多いビジネス環境においては、プレゼンテーションで相手の印象に残る何かしらの「+α」が必要です。たとえ小さなことでも、聞き手が「他とは違う」「この企業に任せてみたい」と感じるような、新しい視点や魅力ある提案があると効果的です。スライドに込めるひと工夫や、資料に盛り込むリアルな事例が、相手の心を動かすきっかけになります。
キャラクター、世界観(設定)、ストーリーの3拍子が揃っている
プレゼンテーションでは、ただ内容を伝えるのではなく、聞き手の感情に訴えかけ、行動を促すことが求められます。魅力的なキャラクター(商材や提案の特徴)、共感を呼ぶ世界観(全体の方向性)、ストーリー性のある構成が三位一体となることで、ビジネスプレゼンの質は一段と高まります。情報を並べるだけではなく、相手の記憶に残る「語り」を意識しましょう。
プレゼンテーション構成のポイント
良いプレゼンテーションの基本的な流れ
プレゼンテーションの構成は、結論を先に述べるスタイルが効果的とされています。以下は、ビジネスシーンで多く用いられる基本的な流れです。
- 1)現状の整理
- 2)課題や問題点の抽出(その背景、要因や原因の因果関係)
- 3)提案の目的
- 4)解決策・提案
- 5)解決策・提案がもたらすメリット(定量的な面でも)
- 6)導入事例、類似事例
- 7)スケジュール→コスト
- 8)(場合によって)競合との比較表
1) 現状の整理
聞き手との認識を揃えるために、現状を正確に把握し、客観的な情報として提示します。スライドや資料には、事実やデータを活用してビジネスの現況を明確に伝えましょう。
2) 課題や問題点の抽出(その背景、要因や原因の因果関係)
プレゼンテーションの中核となるのが、課題の特定です。現状に潜む問題点やその背景・原因を整理し、相手が抱える本質的な課題を明らかにすることが、的確な提案につながります。
3) 提案の目的
提案の目的は、聞き手のニーズや課題に応えるものであるべきです。プレゼンテーションの内容は、この目的に沿って構成され、相手が納得・共感できるストーリーを描くことが求められます。
4) 解決策・提案
整理された情報に基づき、課題をどう解決するかを提示します。実現可能性の高い解決策を、分かりやすいスライドや図表を使って示すことで、説得力が高まります。
5) 解決策・提案がもたらすメリット(定量的な面でも)
提案によって得られる成果を定量・定性的に説明します。コスト削減や業務効率化など、具体的な数字を用いて、ビジネスにもたらす価値を明確にすることが信頼につながります。
6) 導入事例、類似事例
聞き手に安心感を与えるためには、実績や成功事例の紹介が有効です。関連する事例を資料に盛り込み、提案が現実的かつ効果的であることを示しましょう。
7) スケジュール→コスト
提案の実施にかかる期間やコストは、ビジネス判断に直結します。スケジュールの見通しや費用感を具体的に提示することで、プレゼンテーションの実行性が伝わります。
8) (場合によって)競合との比較表
競合他社や他案と比較し、優位性を明示することも効果的です。比較資料やスライドを使って視覚的に示すことで、聞き手が判断しやすくなります。
プレゼンテーションの構成を補強する際に使えるフレームワーク
こうしたプレゼンテーションの流れをさらに補強し、相手に伝わるインパクトある構成に仕上げるために、以下のようなフレームワークを活用することが効果的です。プレゼンの目的や内容に応じて、適切なフレームを選ぶことが、聞き手の理解や納得を引き出すカギになります。
AIDAの法則
「AIDAの法則」というのは、Attention(注意喚起)、Interest(関心)、Desire(欲求)、Action(行動)の頭文字をとった構成法で、1920年代の広告・営業の世界で生まれました。
プレゼンテーションでも、最初に相手の注意を引き、関心を高め、欲求を喚起し、最終的に行動につなげる流れを意識することが大切です。スライドや資料の構成も、この流れを意識して設計すると、聞き手を自然にプレゼンの目的へと導けます。
PREP法
PREP法は、Point(結論)→Reason(理由)→Example(具体例)→Point(再主張)の順で展開するフレームワークです。プレゼンの中で、要点を簡潔かつ論理的に伝えたいときに有効で、聞き手が情報を整理しやすくなります。1つのスライドで1PREPを意識すると、伝えたい内容がすっきりまとまります。
SDS法
SDS法は、Summary(要点)→Details(詳細)→Summary(まとめ)の3段構成で、時間が限られている場面でも相手に情報の要点を伝えやすいフレームです。プレゼンテーション資料の中でも、冒頭やクロージングに効果的に活用できます。
DESC法
DESC法は、Describe(状況の説明)、Express(自分の意見や感情)、Suggest(提案)、Consequences(結果)で構成され、特に相手との合意形成を図るようなプレゼンに適しています。ビジネスの場で対立や懸念を含む内容を話す際、冷静かつ論理的に聞き手に伝えやすくなります。
QCストーリー法
QCストーリーは、品質管理や業務改善の現場で使われる構成法で、「問題発見→要因分析→対策立案→効果確認」といった流れに沿ってプレゼンを構成します。課題解決型の提案においては、ビジネス的な説得力を高めるフレームとして有効です。資料やスライドにも論理的な流れが生まれます。
マジカルナンバー3
「マジカルナンバー3」は、伝えるポイントを「3つに絞る」ことで、聞き手の記憶に残りやすくするという考え方です。内容が多くなりがちなプレゼンテーションでも、「伝えたいことは3つです」と明言することで、情報整理がしやすくなり、印象にも残りやすくなります。
「つかみ」と「オチ」
「つかみ」は、AIDAのAttentionに該当する要素で、プレゼンテーションの冒頭で聞き手の心をつかむための工夫です。ビジュアルやエピソード、印象的な問いかけなど、スライドや話し方を活用して注目を集めましょう。
一方の「オチ(落とし所)」は、プレゼンのゴール=目的にあたります。相手に印象づけたいこと、見積提示、行動喚起など、ビジネスとしての締めくくりが何であるかを明確にすることで、全体の構成も組み立てやすくなります。
プレゼンテーション資料作りのポイント
プレゼンテーションでは、スライドや配布資料を活用して内容を伝える場面が多くあります。ここでは、聞き手に情報が正確かつ効果的に届くようにするための基本的なポイントを5つご紹介します。
1)ビジュアル利用
テキスト情報は最小限に抑え、グラフ・イラスト・チャート・写真など視覚的な要素を活用すると、聞き手にとって理解しやすくなります。
近年はビジネス現場でも動画やアニメーション付きスライドの活用が進んでおり、資料に臨場感を加えたいときに効果的です。
2)アピールポイントはデータ・顧客の声で客観的に示す
ビジネスプレゼンテーションにおいては、スライド内の内容に信頼性を持たせることが重要です。定量的なデータや定性的な評価を通じて、提案の根拠を示すことで、相手に納得感を与えることができます。
「顧客の声」や「導入効果の数値」といった実績情報を資料に含めることで、プレゼンの説得力をさらに高めましょう。
3)商材や提案のメリットは事例を通して語る
提案内容の価値を伝えるには、リアルな事例が効果的です。具体的な成果や活用シーンを示すことで、聞き手は内容を自分ごととして受け取りやすくなり、共感や信頼が生まれます。
プレゼン資料では、スライド内に複数の事例をバランスよく配置することで、提案の幅広さや応用可能性も伝えることができます。
4)プレゼンテーション資料のページ数は「1-3-∞の法則」で
スライドのページ数は、相手の役職や立場に応じて調整するのが効果的です。伝える情報量や資料の構成は、プレゼンの目的や聞き手の関心を踏まえて決定しましょう。
経営層には要点を1ページに集約、マネジメント層には3ページ、現場担当者には必要に応じて詳細な資料を用意するなど、目的と相手に合わせて柔軟に対応することが求められます。
5)神は細部に宿る
細部にまで配慮された資料は、聞き手に「この会社は信頼できる」という印象を与える重要な要素です。
- ビジネス文書として適切な言葉遣い(カタカナ・漢字・敬語など)を選ぶ
- 複数の図表を使う場合は、レイアウト(天地・左右)の整合性を保つ
- 色使いは3色以内に抑え、視認性と統一感を意識する
こうした細部の工夫が、全体として情報の伝わりやすさや信頼感のあるプレゼンテーションにつながります。
プレゼンテーション前に押さえておきたい「聞き手の特性」と「話し手の立ち位置」
ここまで、プレゼンテーションの構成や資料作成といった準備について解説してきましたが、実はそれだけでは不十分です。プレゼンの前には、聞き手(営業であれば顧客)の特性を理解すること、そして話し手である自分自身や自社の立ち位置を整理しておくことが、ビジネスの場で成果を上げるためには欠かせません。
なぜなら、聞き手の属性や期待を無視して情報を一方的に伝えてしまうと、どれだけスライドや内容を作り込んでも、相手に刺さらないプレゼンテーションになってしまうからです。
事前準備の段階で、以下の点を資料や打ち合わせに反映できるよう押さえておきましょう。
聞き手の特性
- 1)企業としての特性、ビジネスの特徴、組織風土を把握する
- 2)社史や沿革、過去の取り組みを理解しておく
- 3)参加者の役職やプロフィール、興味関心を事前に確認する
これらを踏まえることで、プレゼンテーションの内容やスライドの切り口を、聞き手にとって「自分ごと」と感じられるものに調整できます。
話し手の立ち位置
プレゼンテーションにおいて、自分自身の立ち位置を認識することも重要です。相手との関係性や状況に応じて、同じ情報であっても伝え方や資料のトーンを調整することで、説得力が大きく変わります。
- 1)相手の興味・関心が強い場合:深い情報を提示し、納得感を高める
- 2)相手の興味・関心が弱い場合:目的やメリットを強調し、関心を引き出す
- 3)「当て馬」っぽい場合:差別化できる価値や+αの視点を盛り込む
- 4)過去にトラブルがあった場合:信頼回復を意識した構成や資料を準備
- 5)相手が忙しい場合:要点を簡潔に、時間を意識したプレゼン内容に
- 6)ソリの合わない相手の場合:論理性や第三者評価など、客観性重視のスライドに
相手との関係性を踏まえてプレゼンの目的や資料構成を微調整することで、ビジネスの成果につながる「届くプレゼンテーション」に近づけることができます。
プレゼンテーション時の話し方のポイント
プレゼンテーションの目的や内容、資料の準備が整ったら、いよいよ本番です。ここでは、ビジネスシーンで成果につながる話し方のコツをご紹介します。
ゆっくりめ、やや大きめ、メリハリを意識
話し方の基本は、「ゆっくりめ、やや大きめ」に話し始めることです。プレゼンテーションにおいては第一声の印象が重要で、聞き手の集中を促す役割も果たします。
また、話の区切りごとに間を取り、重要な情報を強調することで、スライドや資料の内容がより明確に伝わります。話し方にメリハリをつけることが、相手の理解度と納得感を高めるポイントです。
聞き手とアイコンタクトを取る
スライドばかりに目を落とすのではなく、聞き手の表情や反応を確認しながらプレゼンテーションを進めることが重要です。
特に複数名が参加するビジネスの場では、キーパーソンだけでなく、他の参加者にも視線を向け、全体との一体感を意識します。
また、話し手自身の表情も印象を左右するため、リラックスした笑顔を意識し、信頼感のある空気をつくるよう心がけましょう。
相手を巻き込みながら臨機応変に対応する
プレゼンテーション中に聞き手が資料をめくったり、集中していない様子が見られたら、一方通行になっていないかを見直すサインです。
そのまま進行せず、相手に問いかけをして関心を引き出すことで、双方向のコミュニケーションが生まれます。
もし認識のズレがあれば、スライドや情報をもとにその場で調整し、プレゼンテーションの目的達成を目指しましょう。
準備した内容だけでは十分に応えられないと判断した場合は、後日改めて資料を再構成し、ニーズに応じた再提案の場を設けるのも、ビジネスとしては効果的なアプローチです。
プレゼンテーションスキルを高めるためには
プレゼンテーションのスキルを高めるには、日々の意識と実践の積み重ねが欠かせません。ここでは、話し方や資料の準備力などを総合的に磨くための4つの実践方法をご紹介します。
プレゼン内容を繰り返し練習する
プレゼンテーションの成功は、内容の理解と準備の質にかかっています。話す情報を整理し、何度も繰り返し練習することで自信がつきます。
本番を意識した練習をすることで、話し方のテンポや抑揚、間の取り方が洗練され、聞き手に伝わりやすいプレゼンへと仕上がります。
自分のプレゼンを録音・録画して振り返る
自分の話し方やスライドの見せ方を客観的に確認するためには、録音や録画が効果的です。
声のトーン、スピード、ジェスチャーなどの癖を可視化することで改善点が明確になり、プレゼンテーションのスキル向上につながります。
フィードバックを受けて改善する
他者からのフィードバックは、独りよがりになりがちな話し方や構成を客観的に見直すきっかけになります。
上司や同僚にプレゼン練習を見てもらい、話のわかりやすさ、資料の見せ方、聞き手への配慮など、率直な意見をもらいましょう。フィードバックを受け入れる姿勢も、スキルを伸ばすためには欠かせません。
優れたプレゼンテーションから学ぶ
上手なプレゼンを参考にするのも非常に効果的です。著名なスピーカーやビジネスシーンの実例から、構成や聞き手を引き込む表現、資料の見せ方を学びましょう。
良いプレゼンを分析・模倣することで、自分のスタイルを築くヒントが得られます。
実践型でプレゼンスキルを高める伴走型オンライン研修
プレゼンテーションスキルを高めるには、準備、練習、分析、そして学びが鍵となります。本記事で紹介した具体的なコツを参考に、自身の課題を明確にし、実践を通じて改善を重ねることで、より効果的なプレゼンを実現しましょう。
プレゼンテーションスキルを高めるうえでは、外部の研修に参加することも有効な手段です。
伴走型オンライン営業研修「営業サプリ」プレゼンテーションコースでは、プレゼンテーションのスキルやテクニックを学べることはもちろん、徹底的に実践演習とフィードバックを繰り返すことで、着実にスキルを身につけることができます。少しでも興味を持たれましたらまずは資料をダウンロードしてご覧ください。
プレゼンテーションのノウハウをまとめた資料をダウンロード

この記事の内容を含めた、プレゼンテーションのノウハウをeBookにまとめて無料配布しています。簡単なフォームに入力するだけでダウンロードしていただけます。ぜひご覧ください。
私が開発した「営業サプリ」で営業メンバーを育てませんか?

ここで述べているノウハウやスキルは、読んだだけでも充分勉強になります。しかし、これだけでできるようになるわけではありません。実際の営業場面で「できる」ようになるためには『実践とフィードバック』が必要になります。
私が株式会社サプリと開発した『営業サプリ 売れる営業養成講座』は、営業パーソン自身の営業を前提に実践しながらオンラインで学ぶコースです。しかも専門コーチがマンツーマンで指導する仕組みになっています。
売れる営業パーソンになるスキル大全を身につけるオンライン研修、『営業サプリ』で「売れる」営業パーソンを育てませんか。さあ、営業サプリで営業組織を強くしましょう!
\3分でわかる/
営業サプリ紹介資料 ダウンロード
こちらのフォームにご入力ください(入力時間1分)。*は必須項目です。
- 1. 事業者の氏名又は名称
- 株式会社サプリ
- 2. 個人情報保護管理者の氏名又は職名、所属及び連絡先
-
個人情報保護管理者 代表取締役 酒井雅弘
info[at]sapuri.co.jp
[at]を@マークに変換してお問い合わせください。 - 3. 取得した個人情報の利用目的
- 当該フォームで取得した個人情報は、お問い合わせに関する回答、ご請求いただいた資料の送付、メールマガジンの配信等の目的で利用いたします。また、当社のサービスに関するご案内にも利用させていただくことがございます。
- 4. 当社が取得した個人情報の第三者への委託、提供について
- 当社は、ご本人に関する情報をご本人の同意なしに第三者に委託または提供することはありません。
- 5. 個人情報保護のための安全管理
-
当社は、ご本人の個人情報を保護するための規程類を定め、従業者全員に周知・徹底と啓発・教育を図るとともに、その遵守状況の監査を定期的に実施いたします。
また、ご本人の個人情報を保護するために必要な安全管理措置の維持・向上に努めてまいります。 - 6. 個人情報の開示・訂正・利用停止等の手続
-
ご本人が、当社が保有するご自身の個人情報の、利用目的の通知、開示(第三者提供記録の開示も含みます)、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を求める場合には、下記に連絡を頂くことで、対応致します。
<個人情報お問合せ窓口>
株式会社サプリ 個人情報お問合せ窓口
info[at]sapuri.co.jp
[at]を@マークに変換してお問い合わせください。 - 7. ご提供いただく情報の任意性
- 個人情報のご提供は任意ですが、同意を頂けない場合には、第3項にあります利用目的が達成できない事をご了承いただくこととなります。
- 8. 当社Webサイトの運営について
-
当社サイトでは、ご本人が当社Webサイトを再度訪問されたときなどに、より便利に閲覧して頂けるようCookieという技術を使用することがあります。これは、ご本人のコンピュータが当社Webサイトのどのページに訪れたかを記録しますが、ご本人が当社Webサイトにおいてご自身の個人情報を入力されない限りご本人ご自身を特定、識別することはできません。
Cookieの使用を希望されない場合は、ご本人のブラウザの設定を変更することにより、Cookieの使用を拒否することができます。その場合、一部または全部のサービスがご利用できなくなることがあります。
この記事の情報は公開時点のものです。